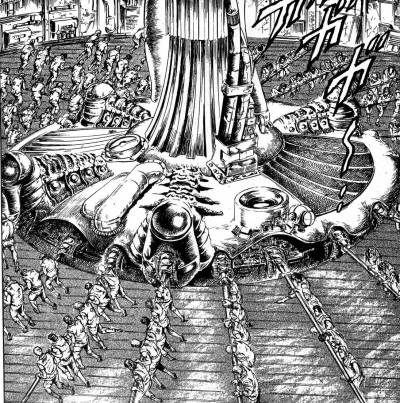事件後に相次ぐSOS 「隠したい」家族の孤立防ぐ手立ては
元農水次官による長男刺殺事件や川崎市の児童ら殺傷事件を受けて、中高年の引きこもりに関する相談が支援団体などに相次いでいる。
家族が身内に引きこもりがいることを「恥」に感じ、周囲に隠して孤立してしまうケースは多く、行政や民間団体への相談に恒常的にどうつなげるかが課題だ。
専門家は「総合的な対策が急務」と訴える。
NPO法人「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」(本部・東京)には、2つの事件が発生して以降、引きこもっている本人や家族からの問い合わせが急増している。
「『引きこもりは危ない人』というイメージで報道されている。どうしたらいいのか」。
4日だけでも数十件の電話やメールが寄せられており、そんな不安を訴える人もいるという。
同NPOは川崎の事件を受けて1日、「家族や本人の受け皿が十分でなく、あるいは困難な状況で放置され、適切な支援につながりにくい実態を示している」
などとする声明を発表。事件は、引きこもりの子が50代、親が80代で困窮する「8050(はちまるごーまる)問題」の社会的孤立の深刻さを映し出したものだと強調した。
引きこもりの支援や治療に長年携わってきた精神科医の宮西照夫・和歌山大学名誉教授は「中高年の引きこもりでは、特に現役時代に社会的な地位が高かった親ほど、
世間体を気にするなどして相談をためらってしまうため、実態が見えてこない傾向がある」と指摘する。
「家族だけに我慢を強いる社会でいいのか」。インターネット上の書き込みには、川崎の事件で児童らを殺傷後に自殺した岩崎隆一容疑者(51)と同居していた
伯父夫婦だけでなく、引きこもりがちだった長男(44)を刺殺した元農水次官の熊沢英昭容疑者(76)に対して、同情や理解を示す内容も少なくない。
中高年の引きこもりは40〜64歳で61万人(内閣府調査)に上るとされ、解決には行政などの第三者の支援が欠かせない。
厚生労働省は各都道府県と政令市に「ひきこもり地域支援センター」を設置しているほか、東京都は今回の事件を受けて、これまで15〜34歳としていた引きこもりの電話・訪問相談事業の対象を35歳以上に拡充した。
https://www.sankei.com/life/news/190604/lif1906040031-n1.html